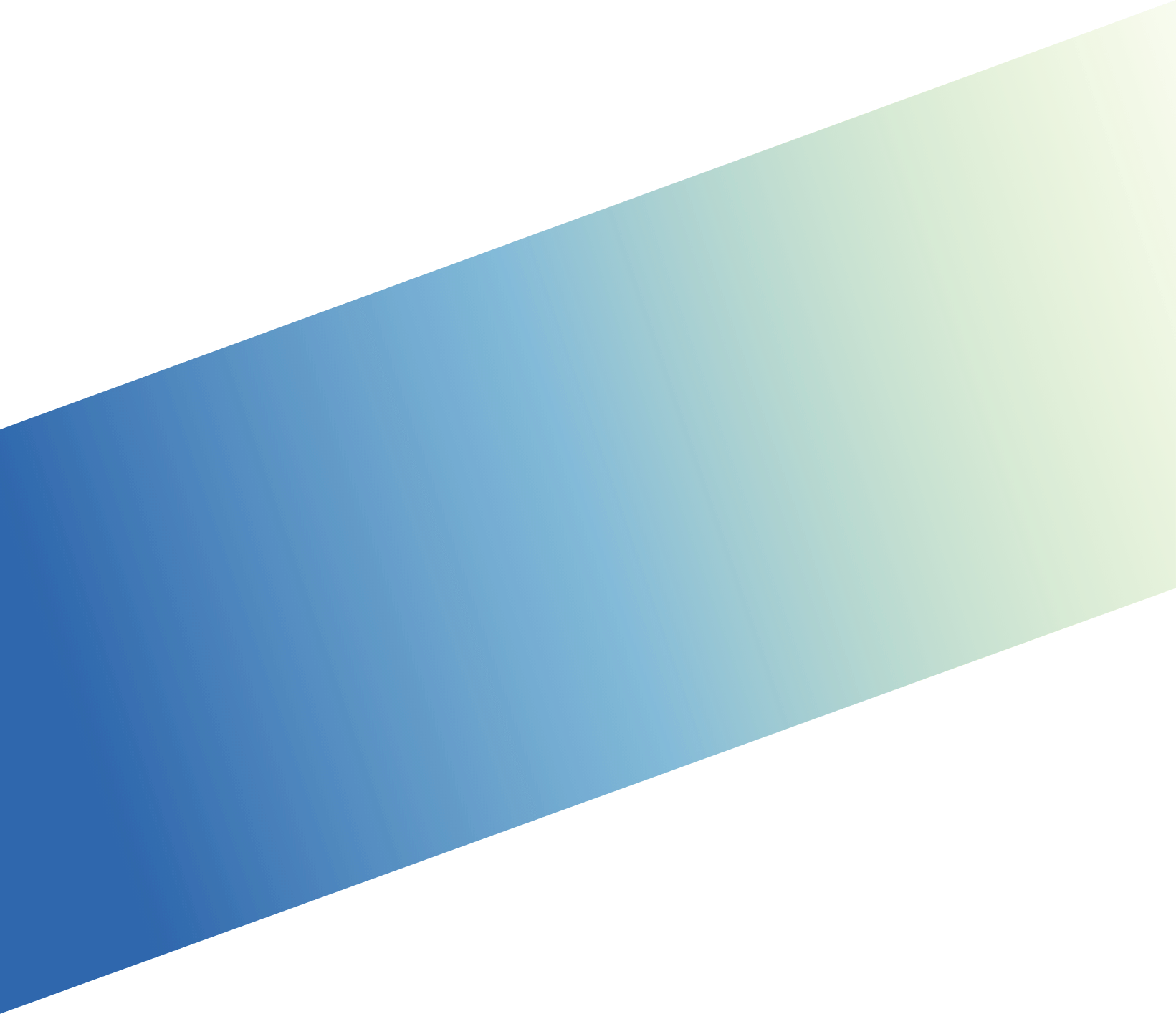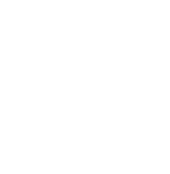

culture talk 02
カルチャートーク

組織の一員としてだけでなく、
「個」の “先端”技術力強化も欠かせない。
さらなる飛躍を目指してNTTデータ先端技術で働くことを選んだ中途入社社員と、大学院でITの専門性を学んだのちに新卒で入社した8年目社員(取材当時)。部署もバックグラウンドも異なる3名に、それぞれの知見を活かしたプロジェクトの関わり方、技術力向上やキャリアアップに繋がる社内のサポート体制等を伺いました。

S.R
セキュリティ&テクノロジーコンサルティング事業本部
セキュリティエンジニア
(2016年入社)
S.R
工学研究科経営工学専攻修了。大学ではセキュリティの研究室に所属し、その専門性を社会で活かすため、中央官庁や金融機関、大手企業等、社会的影響度の大きいセキュリティの技術者として関与できる当社に新卒入社。SOCエンジニアやインシデント対応支援などの経験を経て、8年目を迎える。

K.H
デジタルビジネス事業本部
ソフトウェアエンジニア
(2015年入社)
K.H
環境情報学部卒業。独立系SIer、外資系ITコンサル企業でテクニカルサポート等を担当。新技術をキャッチアップしながら開発に携わる仕事を希望し、入社。社内公募にて部署異動を経験。現在はアジャイル開発のテックリードとしてアーキテクチャ検討のほか、顧客への提案まで幅広く行う。

W.S
基盤ソリューション事業本部
インフラエンジニア
(2018年入社)
W.S
情報通信工学科卒業。前職在籍時にSESとして参画した大手SIerでは、ITインフラ構築における上流工程まで経験を重ねる。次第にネットワーク領域に興味を持ち、大規模通信基盤に携わりたいと入社。前職ではOracleDB開発、オンプレミス開発・運用・保守等を経験。
TOPICS
- Session 01
- 予想外の良い二面性を知る
- Session 02
- 最先端を担っている自分に気がつく瞬間
- Session 03
- 興味の成功体験が先端を歩み続ける秘訣
- Session 04
- 先端で活躍したい人に
「ぜひ」と言える会社

予想外の良い二面性を知る

S.R
私は研究分野のサイバーセキュリティに関して、その成果を実社会で存分に活かし、さらに技術を高めるのであれば当社が最適解だと考えて就職しました。当社の顧客はシステムのダウンや情報漏洩が起きれば社会的インパクトが大きく、それを未然に防ぎ社会の安全・安心を維持する役割の重要さを感じたからです。実際に入社してみて、セキュリティ技術の先陣を切っていく業務内容は想定通りでした。良い意味で予想外だったことは、個人の裁量が大きく自分のやりたい方向を認めてもらいやすい風土でした。入社する前は組織の意向が強く優先される会社であると先入観を抱いていました。

W.S
確かに私も入社後に、自分の意見を言いやすい社風だと感じました。社内の情報共有意識が高く、コミュニケーション力の高い社員も多いですね。また、NTTデータグループ全体に感じたことが、「和」を大切にしていることです。開発のフレームワーク等がしっかり組まれていることから、和が醸成しやすい環境なのかもしれません。一方で、高い技術力を持った方々が集う会社、という入社前の印象はイメージ通りでした。サーバーやストレージ、クラウドに関する高レベルの有識者はもちろん、Ciscoのベンダー資格の最上級であるCCIEを取得している仲間が複数名在籍しており、Slack等を使って技術的な相談をすることがありますが、大変助かっています。

K.H
私も同意見で、顧客や協働者と良い関係を築ける人が多いと感じています。入社前は高度な技術に特化したエキスパートの集団である認識でしたが、マネジメントや営業的な役割もこなせるマルチプレイヤ揃いで、意外な印象を持ちました。そもそも私が当社を選んだ理由は、社会のITインフラの多くを支えるNTTデータグループであり、“先端技術”と社名にあるからには、新技術を用いた開発の機会が必ずあると考えたからです。そしてそれは期待通りでした。




最先端を担っている自分に気がつく瞬間

K.H
入社後、最初の案件では知識が不足していた基盤技術を学び、次にブロックチェーンのR&D案件でNTTデータグループの世界中の仲間とコミュニケーションを取りながら最新技術の動向を知る等、希望通りに新しい技術にキャッチアップできました。現在はアジャイル開発のテックリードとしてアーキテクチャの検討や方式設計、基盤構築等に携わっています。ほかに、アジャイル開発に関する記事を技術雑誌に寄稿したり、アセットを開発したり、プリセールスに協力したりと、やりたいことを幅広くやらせていただいています。学ぶことは多いですが、技術と開発プロセスの最新・最先端を探求しているかもしれないと思うことは少なくありません。

W.S
最先端を担う……まさに私の業務でも一部通ずるものがありますね。異動前はプロジェクトリーダーとして計算系システムのネットワーク基盤運用支援に参画していましたが、品質を重要視するお客さまであり、上流工程から最新技術を取り込む余地があるか品質とのバランスを考慮に入れて要件定義を意識していました。現在は主にNTTデータに納品したネットワーク機器のサービスデスク業務や、NTTデータ向けマネージドサービスの開発業務を担当していますが、日本最大級のSIerのネットワークに重大なインシデントや問題が起きた際に最初に連絡が入るチームに所属しています。その時は現場に常駐しているメンバーとともに解決を図るポジションであることから、NTTデータが当社に最先端のネットワーク技術レベルがあることを期待し、確かな信頼を置いているからといえます。

S.R
サイバーセキュリティの世界においても、最先端であることは常に求められます。攻撃者は常に新しい攻撃手法を研究しており、新しい技術が生まれれば、そこがサイバー攻撃の新たな戦場となるからです。また、いかに防御するか等の対策を考える上でもどのように適応するかを検討しなくてはなりません。私の所属するサイバーセキュリティインテリジェンスセンターでは、日々手口が巧妙化する脅威を分析し、サイバーセキュリティ対策を検討するお客さまの戦略層や対策を実際に行う現場層などの意思決定を支援するための活動である脅威インテリジェンスを提供しています。当社が最先端技術を提供できる存在であるからこそ、最新の脅威に適応した対策をお伝えすることができます。



興味の成功体験が先端を歩み続ける秘訣

W.S
当社の魅力のひとつに社員の向上心への支援の手厚さがあります。会社の方針で取得価値のあるベンダー資格に積極的に挑戦することを奨励していますので、業務時間内でも空き時間を活用して資格勉強も可能ですし、費用も気にせずに受験することができます。機器やアプリケーションのベンダーからの売り込みも早く、当社のソリューション候補として早い段階で検証に携われることもあります。

S.R
最先端の情報が自然と入ってくる環境ですよね。以前、情報セキュリティに関する世界最大級のカンファレンスである「RSA Conference」に参加させていただく機会がありました。有識者の講演を拝聴し、最新の脅威に関する情報を獲得し、発表されたばかりのセキュリティ製品に触れ、ベンダーとも商談する等、セキュリティエンジニアとして貴重な経験を積みました。ほかにも世界最高レベルのセキュリティ教育機関であるSANSのトレーニングも会社負担で受講させていただく等、グローバルの最新動向を積極的に取得する機会を存分に与えてくれる会社だと思います。

K.H
教育面のサポートだけでなく、さまざまな技術領域の有識者が社内に集まり、そうした有識者とコミュニケーションが取りやすい風土であることが、当社の技術水準を最先端へと高めているのだと思います。もし他の分野や領域に興味を持ちましたら、社内公募制度の活用をおすすめします。私自身もアジャイル開発の部門には社内公募制度を利用して異動しましたが、学ぶ分野を自分で選択できる環境も当社の魅力です。




先端で活躍したい人に「ぜひ」と言える会社

K.H
新しい分野に転職をせずに社内で挑戦できることから、技術力を伸ばしたい方、自分の興味ある方向を深めたい方にはとっておきの環境だと思います。ワーク・ライフ・バランスの面でも社員のことを考えてくれるので、仕事への意欲を持ち続けられます。私の直近の目標は、アジャイル開発でスクラムマスターをやること。ゆくゆくはアジャイルコーチとして、笑顔があふれるスクラムチームと、ときめくシステム開発を増やしていきたいと考えています。そのための資格取得や会社との認識合わせをすることができる風土は、貴重だと思います。

S.R
技術的な知見のみならず、実際にお客さまがさらされているサイバーセキュリティの脅威による、安全・安心に関する課題を解決することが求められることから、着実に現在の自分になるまでのレベルアップとなるプロジェクトに携わることができます。最先端に追いつく努力も楽しいと感じられる人には、必ず満足してもらえます。私自身の今後のビジョンは、さまざまな業界や立場でセキュリティ脅威と戦う技術者と意見を交換しつつ、多様性のあるチームを育ててお客さまの課題に挑んでいきたいと考えています。

W.S
自分より技術力が高い先輩が数多く在籍しているため、入社直後はその実力に圧倒されるかもしれません。それでも技術が好きという気持ちを持ち続け、邁進していけば必ず近づくことができると思います。私は組織体制変更による異動も経験しましたが、必ずプラスになります。転職前・異動前・現在の部署、それぞれの環境で培った経験を自組織に還元すべく、部署の垣根を超えた勉強会を実施する等、後輩育成に活かしたいです。
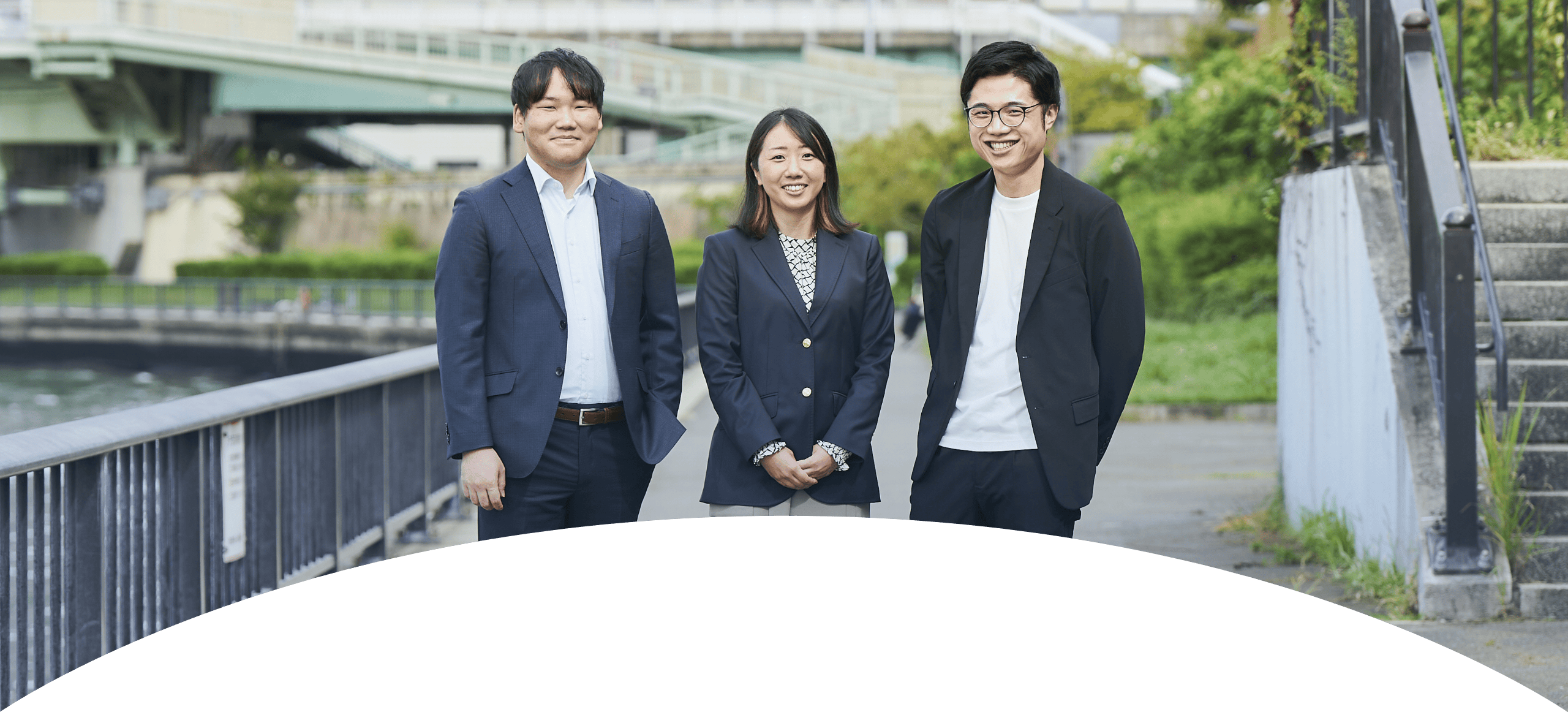
Pride in Technology
~技術への誇り~
三者三様のキャッチアップと
社会へのアウトプットで
努力を楽しさに変える。
3名とも新しい世界を切り開く開拓者精神に満ちており、社内にも同じようなマインドを持った仲間が数多く活躍しています。最先端の技術取得は並大抵ではない中、やりがいに繋がる価値を見出すことが大切です。
「だれもが知るサービスの一部を担うことができたやりがいや、充実感もありました」(W.S)、「教科書では学ぶことができない大規模なお客さま環境特有の情報からサイバー攻撃の挙動を分析するような得難い経験がいくつもありました」(S.R)、「寄稿した技術雑誌が書店に並んでいるのを見て、やりがいを感じました」(K.H)。
教育環境やキャリア支援制度を活用し、注目度の高いプロジェクトにも挑戦しながらスキルアップを目指せる環境です。
※文中の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。