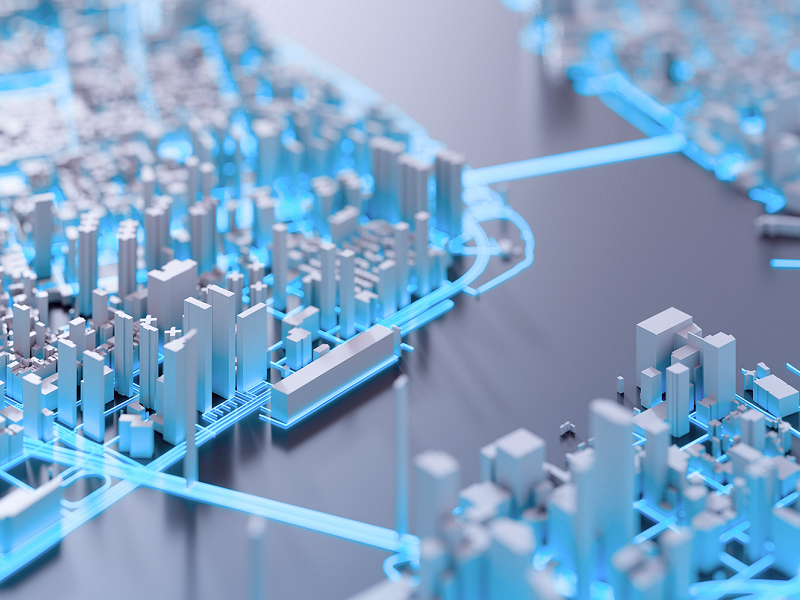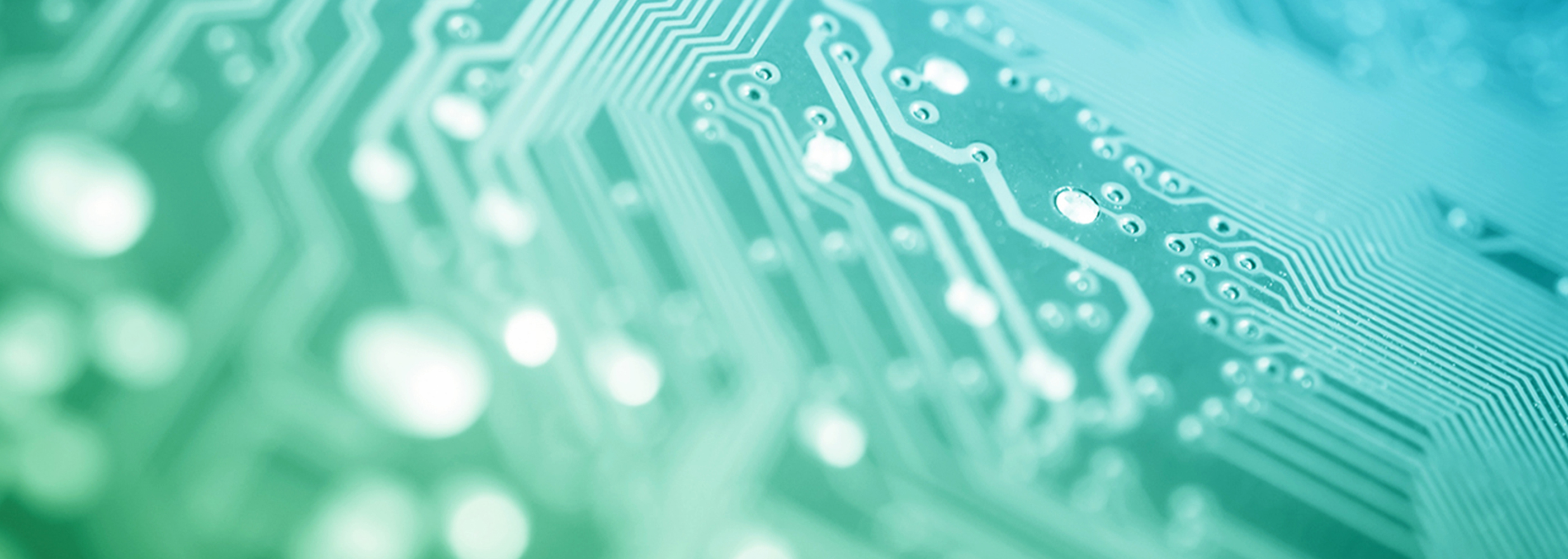第1回 クラウドインフラってなぁに?
Tweet

シダ部長
若い頃は色々な大規模開発プロジェクトで開発者として辣腕を振るい、その後は経験を活かし炎上プロジェクトの火消し人や、先進的技術の R&D などに携わり「受け攻めのシダ」の異名をもつ。

ハブカくん
シダ部長の指揮する部署に配属されたばかりで、シダ部長のもとで流行りの「クラウド」について七転八倒を繰り広げる。

竹本トミー
未来の世界のハコ型ロボット
サービスとしてのインフラ







君は基本的に先進的な技術に関する知識が足りてないので、少しは流行りの技術を追ってみてはどうだい?


いや、私が言いたいのはそれじゃないよ、例えば君は「プライベートクラウド」っていう言葉を知っているかい?




こうして、ハブカくんはシダ部長から言われた「クラウドインフラ」について調べることになったようです。
~ 1週間後 ~



クラウドインフラとは主にインフラに関する機能をクラウドとして貸し出すサービスの事を指します。例えばクラウド界の巨人である Amazon が提供するサービスの AWS では Amazon EC2 と呼ばれるサービスがそれにあたります。
(※1 もちろん、AWS には EC2 以外にもさまざまなインフラサービスがあります)







ハブカくんが調べた Amazon EC2 とはこのうちのコンピュートをリソースとして貸し出しているだろう?


まぁいいや、じゃぁ「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」っていうキーワードについても既に知っているね?

一方のプライベートクラウドはパブリッククラウドとは異なり、クラウドプロバイダーが利用者にサービスを提供するのではなく、利用者が自身の環境に物理リソースや環境を用意しそこにクラウド環境を構築して自身で利用したり、自身がそのクラウドを他者に貸し出したりする形態となっています。



パブリッククラウドに対してのプライベートクラウドのメリット・デメリットは多面的な見方をしないと評価ができないということなんだよ。たとえば一例で挙げると以下のようなことが言えるね。
| パブリッククラウド | プライベートクラウド | |
|---|---|---|
| コスト面 | メリット:スモールスタートが可能なため、イニシャルコストを抑えることが可能。その他発生する固定費が「利用料」のみであるため、コスト計算が用意。 | メリット:規模が大きくなるにつれ規模の経済によるメリットを発生させることができるため、場合によってはパブリッククラウドより費用が抑えられる可能性あり。 |
| デメリット:規模が大きくなるにつれ、利用料もリニアに近い状態で増加する。(クラウドサービスによっては年単位の契約でコストを低減させるオプションがあったり、一定以上は課金されないオプションがあったりする) | デメリット:イニシャルコストが(パブリッククラウドに比べて)高くつく傾向にある。 | |
| 安全性 | メリット:サービス提供側のセキュリティ対策を簡単に利用できるため、セキュリティ対策にかかるコストが少なくなる。 | メリット:自前で可能な限りいくらでもセキュリティ対策を施すことが可能。 |
| デメリット:サービス提供側のセキュリティに依存する部分があるため、利用者が行なえるセキュリティ対策には限界が生じる。 | デメリット:「ローカルは安全」という誤解からセキュリティ対策が蔑ろにされ、パブリッククラウドより安全性の低いクラウドシステムとなるケースがある。 | |
| 運用性 | メリット:インターネットに繋がる環境であればどこからでも運用できる。運用自体がサービス化されている場合がある。 | メリット:物理的にアクセスできればどんなことも可能。何かあった際に最終的に自分達でどこまでも対応可能。 |
| デメリット:インターネットに接続できない場合、ほとんど何もできない。何かあった際にサービス提供者にサポートしてもらう必要がある。 | デメリット:運用に関して物理的なことまで面倒を見ないといけない。 | |
| 拡張性 | メリット:サービス提供者が提供するサービスを組み合わせてより良い機能を実装できる可能性がある。またサービス提供者が提供する機能であるため、既存の機能との親和性が高いケースが多い。 | メリット:自前でどこまでも拡張することが可能。ニッチな要求に対してもコストをかければ応じることが可能。 |
| デメリット:サービス提供者が提供するサービスをカスタマイズできる範囲が限られていたり、全くカスタマイズできない可能性がある。 | デメリット:自由に拡張が可能だが、他のクラウドとの互換性が失なわれる可能性もある。 | |
| 耐障害性 | メリット:サービス提供者が提供する各種の仕組みおよびサービスを利用することで低コストで耐故障性を持たせたシステムを作ることが可能。 | メリット:自分達が保有する耐故障性が担保された設備にクラウドシステムを構築することが可能。また耐故障性を上げるために自分達で自由に対策できる。 |
| デメリット:耐故障性をある一定以上に上げるためには更に他のパブリッククラウドをも利用する必要が出てくる。 | デメリット:ゼロから耐故障性を上げるためには設備投資のイニシャルコストがパブリッククラウドより高くなる。 |












| イニシャルコスト | ランニングコスト | |
|---|---|---|
| 施設 | DCの契約費やラックにかかる費用 | 施設の利用料 |
| 通信回線 | 通信回線の契約費 | 通信回線の利用料 |
| ハードウェア | 購入費用 | 故障時の交換費用 |
| 人件費 | 構築に関する一切の費用 | 運用者の費用 |
| 交通・運輸費 | DCへの移動費用や物品の輸送費用 | メンテナンスなどによるDCへの移動費用 |


もちろん、本当にごく小規模な利用の場合はパブリッククラウドのみで足りるケースがほとんどだけどね。


プライベートクラウドだってクラウドコンピューティングを形成するエコシステムのひとつであるという認識を持ってもらえればもう少し違うイメージになっていたかもしれないね。


Tweet